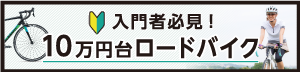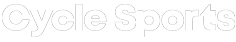ニュース
南アフリカ、荒野のエンデュランス・レースに挑む ブライトリングの新たなる使命
レース
2019.01.05
スポーティかつエレガントへと新たな舵を取るブライトリングが、その挑戦として選んだ先は、南アフリカの老舗ロングディスタンスレース。青年編集部員の目線の先にある、スクワッドのミッションとは?
(text:Kyohei Eriguchi photo:Breitling、Kyohei Eriguchi)
Presented by Breitling
(text:Kyohei Eriguchi photo:Breitling、Kyohei Eriguchi)
Presented by Breitling
Breitling Squad:ブライトリング・スクワッド
人生でいつか叶えたい夢、というものを誰もが持っているだろう。それはきっと人によって千差万別で、貴重なものを手に入れること、その時そこでしか見ることのできない景色を見ること、あるいは僕たち自転車乗りにとっては遠く離れた異国の地を走る、なんてこともあるかもしれない。
誰にとっても夢を持つことはどこまでも自由だ。でも正直なところ、それを追い求めるためのチャンスは、そう多くは巡ってこない。おそらくほんのわずか、一瞬のタイミングにしか。
そんなことを頭に巡らせながら、僕は今、荒野を一人走っている。目の前は、遠く地平線まで続いていくまっすぐなアップダウンの舗装路。脇にはこげ茶色の岩肌が不可思議な角度で突っ立つ山々がそびえる。それに加えて、冬の東京から一転、ここは夏真っ盛りで容赦のない日差しが影をくっきりと作る。僕は今、ブライトリング・スクワッドの一員として、その集団からちぎれ、南アフリカのなんてことない路上をひとり走っている。
ブライトリングと聞いて唐突と思うかもしれないが、好事家ならその名は言わずもがなだろう。航空機のプロフェッショナル・パイロットが愛用するクロノグラフという印象のブランドが、なぜ自転車チームとしてこの南アフリカのレースを走っているのか。その説明は、今は少しおいておこう。それよりも重要なのは、今どうやってこのピンチを切り抜けるか、ということだ。
総距離202kmのまだ80km地点でしかないのに、少し気を抜いて写真を撮りながら坂を上っていたら、あっという間に彼らはピークを過ぎて、恐ろしい速度で長い長い坂を駆け下りていってしまった。しかもその先頭を引くのはヴィンチェンツォ・ニバリだ。あのバーレーン・メリダの、メッシーナの鮫。そんな速度の集団に、これから僕がひとりで追いつかなくてはいけないらしい。
ブライトリングはその活躍のフィールドをこれまでの空だけでなく陸や海、あるいは社会的な側面へもその絆を深めていくべく、ブライトリング・スクワッド構想をスタートした。この時計を愛するプロフェッショナルやスターと志を共にし、同じゴールを目指すことで、彼、彼女たちの持つ情熱や世界観が改めてブライトリングの価値と結び付いていく。
今回はそのなかのひとつトライアスロン・スクワッドの挑戦として、南アフリカで開催されている由緒あるエンデュランスレース「コロネーション・ダブル・センチュリー」に出走することとなった。それと同時に掲げた目標というのが、メンバー一人あたり1万ドルを南アフリカの自転車を活用した慈善団体・クベカに寄付してもらう、というもの。いわゆるプレミアム・チャリティーライドという側面も持つ。
そしてスペシャルゲストの一人として、ニバリが招かれた。だけどそもそも、このトライアスロン・スクワッドのメンバー自体がニバリに負けず劣らずのキャリアの持ち主で、北京五輪の金メダリスト、ヤン・フロデノからアイアンマンのワールドチャンピオンのダニエラ・リフやクリス・〝マッカ〞・マコーマックと、本当にそうそうたる顔ぶれ。ゲストの他にはMTB世界選手権覇者のニノ・シューターまでいる。
その彼らとともにニコニコと笑いながら一緒に走るブライトリングのCEO、ジョージ・カーン氏やまわりのスタッフたちはその雰囲気からも、サイクリングを愛していて年単位で走り込んでいることが分かる。事前に聞いてはいたけど、その彼らと同じペースで走ることがどうなるかということを想定するほど、僕は思慮深くなかったようだ。
と、ぼやいていても仕方がないが、案の定100kmを過ぎても補給は見つからず、ボトルはもうカラカラ。幸いバックポケットには十分すぎるくらいの極甘ジェルを詰め込んでいたので、ハンガーノックの心配はなさそうだ。
60km地点にあった標高800mの山岳を越えたときは、今日の自分の脚の調子の良さとコルナゴ・C64の剛性感がマッチして最高の気分だったが、それがまだ100kmもあると思った時点で、この脚はいつまで持つんだろうという恐れに変わる。しかも一人だ。リタイヤの一言も浮かぶも、この路上ではサポートカーが来る気配はないし、たとえ止まったところで木陰もないなか待ちぼうけするだけ。
ただこみ上げる渇きとともに視界はぼんやりしてくる。11月に熱中症か。と、これまでの乾いた風の音とは異なる音が響いてきた。振り返ると、確かに大集団が後方から迫ってくる。他チームの寄せ集めが追い抜いていくその最後尾に、しがみつくように乗りこんだ。目の前の黒人のおっちゃんの背中にくっつくように走り続け、からがらブライトリングの一団が休憩している補給ブースにたどり着いた。
帰ってくるなりスペイン人のボニーが陽気に「どこ行っていたんだよ!このオーストリッチめっちゃうまいぞ食っとけよ!」と渡してくれたのは、バターとダチョウ肉がたっぷりと挟まれたライ麦パンだった。酷暑のライドの途中の食事にしてはそのワイルドさにめまいがするが、まだ先は長いとコーラとともに流し込む。
再スタート後のコースは、多少のアップダウンはあるが平坦基調。またニバリを先頭に列車は動き始める。引き続き視界の果てまでまっすぐな道を行くイエローカラーは、スローペースだ。ほっと一息ついていると、脇から別チームのライダーたちが、こちらの集団を追い越して何やら話しかけてきている。どうやら先頭のニバリを目当てに、セルフィーをしているようだ。
集団を追い越すたびに、わらわらとライダーが集まってセルフィー。またひとつ追い越して、セルフィー。あれ、なんだかきついぞ? どうやらニバリが明らかに巡航速度を上げてきている。平地の集団後方を走っているだけなのに、どんどん心拍が上がっていく。けれど、もはやちぎれるわけにはいかない。生殺しの前に補給だととっさにジェルを取り出す。
するとその瞬間、道路脇から子どもが駆け寄ってくる。「スウィート!スウィート!」。着古し色あせたTシャツ姿の子どもたちは、まるでレース中に選手に補給食を渡すかのように手を伸ばし、道沿いを走るライダーたちに物を乞いはじめる。
緑美しいワイン畑を通り過ぎていくたびに、子どもたちは続々と現れる。まるで遊ぶかのごとく、けれど切実に。走る僕らのバックポケットに詰めこまれた甘いお菓子を、あるいは補食し終わったゴミのその残りを手に入れるべく。
僕はそのとき補給食を投げ渡すべきだったかと聞かれたら、そんな必要は全くなかったと思う。けれど路上では自転車乗りが夢中で走り、その舗装が途切れた側では甘いお菓子にありつくべく手を伸ばす。それは事実だし、僕がここ南アフリカで知る現実だ。
集団は走り続ける。コースプロフィールでは微細な上下、だけれども実際の光景は、終わりのないアップダウン。レース強度によって終わり始めた脚を僕はなんとか回しつつ、上りが始まるたび集団にくらいつく。それは脂汗がにじむような、痛みを伴う巡航だった。徐々に集団から離れていく。背中を押された。
「ここまで走ってきて、あなたは十分強いのだから、これくらい越えていけるわ」
ダニエラに背中を押されて上る。たぶんぎりぎり大丈夫と思うのだけど。そう答えるが、また次の上りで遅れ、あと少しだから、前に付いて行きなさいとまた押され始める。
彼女はすでに夢を叶えた人だと思う。本当にすばらしい栄誉を勝ち取ったのだから。ただそのために、あるいは今も、彼女はどれほど強くそれを追い求めたのだろうか。彼女が本当にまぶしく感じ、自分の回らない脚に涙が出そうになった。でも、脚を止めるわけにも、チームでの完走を諦めるわけにもいかない。僕は今、夢のような状況で走っている。それを掴むべく、走っている。
農園の子どもたちは、どんな夢を抱えているだろう。みんな、通り過ぎていった自転車選手たちを憧れとして、その記憶に焼き付けていくだろうか。その一人へ自転車が届けば、そこから新しい世界は拓け、己の夢を叶えるためのきっかけになるのなら。今僕が走る意味は、自分のためである以上に、誰かが夢を追い求める力のひとつになることだ。あと1km、また長い上り坂が見えている。腕のクロノグラフはきっかり8時間を越えた。その先にはまだ、南アフリカの荒野が待っていた。
クベカ:自転車を寄付することはその子どもたちの人生を変える
プロツアーチームの名前に入っていたことで記憶に新しい、「Qhubeka(クベカ)」は南アフリカの慈善団体。「自転車で人々を前進させる」ことを掲げ、子どもたちへ自転車を届けることで、彼、彼女たちの日常の交通手段となり、それは学校や職場、あるいは病院へ移動することができるようになる。それは生活を変えていくと同時に、スポーツとして夢を持ってもらう活動でもある。ブライトリングはこの活動のサポートを行うというのが、レース出走のもう一つの目的でもあった。写真はジョージ・カーン氏とトライアスロン・スクワッドのメンバー、クベカによってバイクがサポートされたシカゴの町の子どもたち。
問・ブライトリング・ジャパン
問・ブライトリング・ジャパン